日本において、塩は余り体に良いものとはされません。
むしろ、摂りすぎると健康を害するとされ、悪者扱いされる事が多いと思います。
塩は血圧を上げ、各種癌や循環器疾患の発症を高めると言われます。
減塩は日本に定着し、減塩醤油などの商品が大手をふるっています。
厚生労働省は1日の塩分摂取量を10g未満に設定し、その基準は非常に厳しいものとなっています。
まるでタバコのように肩身が狭くなっている塩ですが、果たしてそんなに体に悪い物でしょうか?
塩に含まれるナトリウムは人体に必要不可欠で、欠乏すると死に直結します。
ヒトは砂糖が無くても生きて行けますが、塩無しに生きる事は出来ません。
戦争の時に塩が足りず、多くの人が命を落としたというのは有名な話です。
また、現在でも極端な塩分制限により、昏睡状態となって病院に運ばれる人や死亡する人もいます。
人間の体液は約0.85%の塩分濃度に保たれており、体内の水分量、PH、栄養の消化吸収、神経伝達など、塩はあらゆる生命活動に従事しています。
我々が生まれた大元である母なる海も塩で満ちており、そこには今でも生命が溢れかえっています。
そんな塩が果たしてそこまで危険でしょうか?
わざわざ減塩する必要があるのでしょうか?
今日はこの話をしたいと思います。
塩の実態、そして塩とのあるべき付き合い方についてお伝えしていきますので、興味ある方はお付き合い下さい。
驚きの研究結果
まず結論から言いたいと思いますが、個人的には塩が人体に害を及ぼすという事は無く、健康のために減塩する必要は無いと考えています。
その事がよく分かる1つの実験をご紹介しましょう。
1998年、医学雑誌「ランセット」で発表されたものです。
25~75歳の成人約21万人を対象に、食塩の摂取量によって少ない人から多い人まで4グループに分け、死亡率を比較しました。
最も食塩の摂取量が少ないグループは、1日当たり男性で2.64g、女性で1.70g。
逆に、最も摂取量が多いグループは、1日当たり男性で11.52g、女性で7.89g。
その結果、死亡率が最も低かったのは、食塩摂取量が最も多いグループでした。
そして、食塩摂取量が少なくなるにつれ、死亡率が高くなっていきました。
高血圧や脳卒中も、食塩摂取量が少ない程、多いという結果になっています。
勿論、1つの実験で全てを決めつけるのは早計ですが、これだけ大規模の実験で示された結果は1つの参考になると思います。
高血圧の本当のところ
では逆に塩が体に悪い事を示すようなデータは無いのでしょうか?
勿論あります。
これは減塩運動のきっかけにもなったものですが、1960年、アメリカのダール博士が行ったものです。
食塩摂取量の多い日本人と少ないエスキモーの高血圧を調べ、食塩摂取量と高血圧患者にの関係を調べました。
すると、そこにはキレイな相関関係が得られたのです。
また、塩をほとんど摂取しない南米アマゾンに住むヤノマミ族という部族がいるのですが、彼らの血圧も標準より低い事がわかりました。
こうした研究により、塩の摂り過ぎが高血圧に繋がるとされ、日本を筆頭に減塩運動が行われるようになりました。
しかし、実はこの研究結果、今では揺らいでいます。
それは1988年、世界32ヶ国、1万人を対象にしたインターソルトという大規模調査で示されました。
調査の結果、塩の摂取が1日3g以下の民族では高血圧は少なく、1日30g以上の民族では高血圧が多い事がわかりました。
これだけ見ると何も変わってないように見えますが、実は3g~30g摂取するという中間にいる大多数の民族においては、食塩摂取と血圧の相関関係は認められなかったのです。
つまり、1日30g以上という異常な量を摂取すれば別ですが、現実的な摂取量では塩の摂り過ぎが高血圧に繋がる根拠は無いという事です。
勿論、食塩により血圧の上がりやすい人がいるのも事実です。
ヒトには塩の感受性に違いがあり、食塩感受性のある人と食塩抵抗性のある人がいる事がわかっています。
これは完全に遺伝の問題で、前者は少しの塩で血圧が上がり、後者は相当量の塩を食べても血圧が上がりません。
ただ、高血圧研究の第一人者と言われる青木博士によると、食塩感受性のある人は高血圧患者でも0.2~0.3%だとそうです。
血圧の上がりやすい層でこの少数なのですから、一般層ではもっと少なくなります。
つまり、塩の摂り過ぎで血圧が上がる人はかなり稀という事です。
また、臨床の場でも、高血圧に減塩の効果は無いという報告がたくさんあります。
高血圧の犯人は塩では無いのです。
日本人と塩
それでも日本人は食塩を摂取し過ぎるから、控えた方が良いという意見もあると思います。
確かに国際的に見て、日本人は食塩摂取量が非常に多く、世界でもトップ3に入ります。
しかし、同時に日本は世界一の長寿国でもあります。
これは塩が日本人の健康を支えているとも考えられないでしょうか?
塩が不足すると無気力、食欲不振、精力減退などに繋がるという専門家も少なくありません。
前途の青木博士はこんな事を言ってます。
「ビタミンの欠乏は特定の病気を引き起こすだけだが、塩の欠乏は命を奪う」
イシハラクリニックの石原医師はこんな事を言ってます。
「塩を取れば体が温まり、免疫力が上がって健康になる」
長崎で被爆した患者とスタッフ70名を1人残らず救った秋月辰一郎医学博士はこんな事を言ってます。
「原爆を受けた人には玄米飯にうんと塩をつけて食べさせろ、塩辛い味噌汁も飲ませろ、そして甘い物は絶対避けさせろ」
勿論、極端に塩を摂り過ぎるのは危険です。
インターソルトの実験でも1日30g以上摂取すると、高血圧のリスクが高まる事がわかっています。
しかし、そもそも塩はそんなに摂れません。
塩は砂糖と違って大量に食べようとすると、塩辛くてマズイと感じ、体が拒否するようになっています。
砂糖はいくら甘くても食べられるし、病みつきにもなりますが、塩はそうはなりません。
必要以上な量が入ってくると危険と判断され、勝手に自粛されるようになっているため、過剰摂取は滅多に起こらないのです。
仮に、塩を食べ過ぎてしまったとしても、その分、水を飲めば問題ありません。
体液の塩分濃度がいくら濃くなったと言っても、それを中和する量の水が入ってくれば大丈夫です。
これは専門家も言っている事ですが、かなりの高塩分食を摂ったとしても、水を十分飲んで尿を排泄する能力があれば、血圧は上昇しないのです。
ですから、わざわざ減塩する必要はありません。
むしろ、日本人は積極的に塩を摂取すべきだと思っています。
日本は高温多湿の国で、汗をかきやすく、塩分を失いやすい環境にいます。
しかも、日本人が好む植物性食品はナトリウムよりもカリウムが豊富です。
カリウムは余分なナトリウムを排泄するので、日本人は余計にナトリウムを補う必要があります。
日本には醤油、漬物、味噌汁などの塩辛い文化が根付いていますが、それにもちゃんと理由があっての事なのです。
塩のクオリティ
ここまでの内容を見て、
「減塩はやめだ!」「塩をいっぱい食べよう!」
と思った方は少なくないと思いますが、しかし、それを実践するのは少しお待ち下さい。
確かに僕は減塩は必要ない、塩は積極的に摂るべきと思っていますが、それは「良い塩」に限っての話です。
良い塩とは我々の体液と近いバランスでミネラルを保有している塩を指します。
別の言い方をすると、海に近いミネラルバランスです。
生命の体液は海と酷似している事がわかっており、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、リン、硫黄など、様々なミネラルをバランス良く含んでいます。
しかし、残念ながら日本に売られている市販の塩は、そのバランスを極端に欠いています。
分かっている人も多いと思いますが、日本の塩のほとんどは塩化ナトリウム含有量が99%を超えており、最早塩と呼べるようなものではありません。
最も分かりやすいのが「精製塩」と呼ばれるもので、イオン交換膜という製法で生産された塩です。
日本市場の約7割を独占しており、ほとんどの人がこの塩を使っています。
そしてもう1つ、海外の天日塩を輸入して日本の海水に溶かし再生させた「再製塩」と呼ばれるものもあります。
実はこれが厄介で、「天日塩」という表記のために良い塩と勘違いしてしまう人が多いのですが、全くそうではありません。
再製塩の原料となる外国の天日塩はメキシコかオーストラリアのものですが、これは高濃度の塩化ナトリウムで構成されています。
しかも、大量生産の工業用として作られているために不純物が多く、日本で再生した時に更に塩化ナトリウムの濃度が高くなります。
結果、再製塩も精製塩と同様に塩化ナトリウムの含有量が99%を超えてしまいます。
そして、こういう塩を摂り過ぎたら、我々は体を壊します。
バランスを欠いたものを食べれば、バランスを崩すのは当たり前です。
高血圧を引き起こすし、死亡率も高まります。
被爆患者を救った秋月博士が使っていた塩も、当時はイオン交換膜の技術がまだ存在せず、必然と良い塩になっていただけで、現代の塩を使っていたら確実に死者を出していたと思います。
1つの栄養を鋭利に突出した食品は体を壊します。
白米しかり、白砂糖しかり、食パンしかり、精製食品が健康被害をもたらすのは周知の通りです。
塩の選び方
塩は良い塩を選ぶ必要があります。
精製塩や再製塩では無く、ミネラルを含んだ良い塩を食べると血圧は低下します。
塩化ナトリウムまみれの塩を、カリウムとマグネシウムを含む塩に変えると、老人の血圧を下げる事もわかっています。
良い塩に含まれるミネラルは、上がった血圧を相殺する効果を生み出します。
塩は減らすのではなく、どんな塩を摂るべきかを考えるのが大事なのです。
その塩の選び方ですが、基本は原料に日本の海水を使っていて、イオン交換膜以外の方法で製造しているものです。
また、海外の塩であれば韓国かフランスのものを選ぶのが良いと思います。
この2ヶ国は塩化ナトリウムの含有量に対して独自の基準が許されており、特に韓国の塩は世界でも最高峰と言われています。
良い塩はそれなりに高価ですが、その位は出す価値があると思います。
塩は調味料の代表格で、あらゆる食品に使われます。
塩のクオリティが食事のクオリティに繋がり、長い目で見た健康を左右します。
ちなみに、外食では高級店でない限り精製塩か再製塩が使われるため、そういう意味でも出来るだけ避けたいところです。
自分の目の届く範囲で良い食材を使っていく事が本当に健康的な事と思います。
という事で、今日は塩の回でしたが最後に纏めです。
減塩は健康的ではありません。
塩はもっと積極的に摂るべきです。
但し、良い塩に限って。
PS:
常識と思っていたものが、よく調べたら違かったという事は多々あります。
紫外線は本当に悪か?という記事もその顕著な一例です。

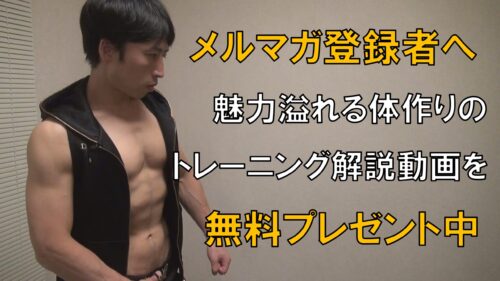




記事の内容に同意します。
良い塩とは加熱を一切しない天日干し完全自然塩のみに限られるべきです。
残念ながら自然塩と表記のあるほとんど製品は加熱加工されています。
塩を精製する過程で高熱が加えられると塩素とナトリウムが強固に結合し体内に入っても分離しません。
尿や汗として排泄されるべき塩素がナトリウムと結合したまま体内に残ることで高血圧を引き起こします。
完全自然塩でフランス産であればフルール・ド・セル、ゲランドなど有名ですが、韓国の塩が良いとは初耳です。
誤解があると思われるのが長寿=健康であるという論調です。
長寿であることと、健康であることは分けて考えられるべきですよ。
健康年齢なんて言葉もありますし。
ちなみに塩辛い物を食べると空腹感が増し、結果肥満につながる可能性が指摘されているのはご存知でしょうか?
そして不健康な肥満体型の方のほうが長寿という研究結果があります。
でもこんな長寿は嬉しくないですよね。
また、別に塩辛くても水飲んでればいいやんという論調ですが、それならむしろ適切な塩の量を提示してあげればよろしいかと。
余分にシオを摂取して水飲めば、内臓に負担がかかります。
一般的な指標で言えば日本人は10g一日でいんじゃない?とかもっと適切な書き方があるのではないかと。
日本だけでも地域の伝統や慣習で塩分濃度が高い食事が好まれていたりしますし、個人間の運動強度も違います。
塩不足で昏睡というのも、マラソン中にスポーツドリンクでも塩分供給が追いつかなかった時に起こった一時的なショックや、自分の喉の乾きや体温変化に気づかないお年寄りに多く見られるものにすぎず、その辺の若年層や中年層がバタバタ倒れてるわけではないですよね?
水分不足の熱中症なら報道されてますが、それを塩だけの問題ですとは言えませんよね?
夏場なので別に今時期に少し増やしても問題はありませんが、冬なんかははっきりむくみますよ、汗かきませんから。
色々論文を引っ張ってくると、私だってどんな方向にでも健康記事でも書けます。
しかし論文の再現性は限定条件下という制限つきであることが多いですよ。
健康の真実!みたいなことを書こうとするとどうしても、現実に当てはめて考えると矛盾しそうな論文ばっかりひっぱることになるので、投稿する前には、自分の身体には当てはまってるかくらい考えたほうが良いかと思います。
少なくとも私は今の自分が健康である保証もないのに、また今後も健康診断の回数が増える予定もないのにわざわざ内臓に負担をかけたいとは思わない記事でした。
アーメン。