「水をたくさん飲むのは本当に良いのか?」
以前、コメントでこのような質問を頂きましたが、水への疑問を頂いている方は結構いるようです。
僕は基本的に「水は暇さえあれば飲んでおけ」という派なのですが、なるほど世の中には水を危険視する声がそれなりに上がっています。
例えば、
「水を飲み過ぎるとむくむ」
「水は体を冷やしてしまうらしい」
と言う人もいるし、
「頭痛とか目まいとか便秘の原因にもなる」
「アトピーとか鼻炎とか喘息にもなるらしい」
なんて事を言う人もいるし、
「漢方では水毒なんて言葉もあるぜよ」
こんな事が書かれているのも事実です。
一般的に水は1.5~2Lを目安にたくさん飲みましょうと言われますが、一方でネガティブな情報も出回っており、そこで混乱してしてしまう人がいるようですので、今日はこの辺を考えてみたいと思います。
理屈と実感
まず最初に自分の立場を明らかにしておきますが、冒頭でも言った通り、僕は水はたくさん飲んだ方が良いと思っています。
最低でも1日2L、できれば3L以上という意見です。
この主張の最も根底にあるのは、僕自身が水をたくさん飲む事で健康になった実感があるからです。
ニキビが消えたり、慢性頭痛が治ったり、便秘が治ったり、モチベーションが上がったり、様々な体調改善を肌で感じています。
そして、僕の周りにも同様に水をたくさん飲んで、体調が改善した方がたくさんいます。
もうそれは山のように知っています。
しかし、逆に水をたくさん飲んで不健康になった人を知りません。
こういった実体験が根本の支えとなって水はたくさん飲んで良む物という考えを持っています。
この前提がある上で、今から理屈も解説していきますが、その前に大事な事なので覚えておいて欲しい事があります。
最も大切なのは「実感」です。
理屈ではありません。
心の弱い方はちょっと理屈をこねられてしまうと自分の信じていた物が急に疑わしくなってしまいますが、正しい事はだいたい体が知っています。
自分が試して、長期的に調子が良くなっていれば、それは問題無いと思います。
少なくとも、あなたには合っているはずです。
僕は情報を発信する立場上、ゴリゴリと理屈もこねますが、有用性という意味で、体験や結果に勝るものはありません。
まずはこの事を十分に頭に入れておいて下さい。
では、前置きはこの位にして、まずはネットで囁かれている水が与える害が本当なのかを検討してみたいと思います。
むくみ
水を飲み過ぎるとむくむという方がいます。
これは単純に水分が体に蓄積されてしまうという理由だと思いますが、それは余りにも浅はかというか、目先しか見えていないと思います。
僕が知る限り、むくみの本当の原因は「アシドーシス」です。
アシドーシスとは体液のPHが酸性に傾いた状態ですが、これは体にとっては非常に危険な状態です。
本来、体液は中性や弱アルカリ性で保たれているので、このバランスが崩れると様々な体調不良が起こります。
癌患者は例外無く血液が酸性になっているのは有名な話で、何かしら病を患う人は大抵アシドーシスが起こっています。
これを防ぐために体は何とか体液を中性にしようとしますが、その一つの方法として細胞は水を摂り込みます。
中性である水を抱え込む事で酸性に傾いた体液を少しでも中和しようとするわけです。
しかし、水を抱え込むわけですからその過程で、組織は当然水ぶくれを起こして太ります。
これがむくみです。
つまり、水の飲み過ぎでむくむのではなく、体が酸性に傾いているからむくむのです。
更に言えば、むくんだのは良いという事です。
もし、アシドーシスが起こっているにも関わらず細胞が水を摂り込まなければ、体は酸性に傾いたままで大きなダメージを受ける事になります。
体で起こる事に無意味な事はありません。
風邪を引くと免疫活性のために熱が上がるのと同じで、むくみが発生しているという事は、むくまなければいけない状態にあるという事です。
こういうのを薬で症状だけ消そうとするのが西洋医学の困ったところですが、要はむくみの原因は水では無いと言うという事です。
アシドーシスが起こってさえいなければ、水はどれだけ飲んでも適切に体外に排泄されます。
アシドーシスが起こる最も大きな要因は酸性の食べ物を食べる事です。
肉類、乳製品類、ケーキ、コーラなど、こうした食事の摂り過ぎで起こりますので、むくみが気になるなら、水を抑えるのではなく、食生活を改善すべきです。
ちなみに、血液のアシドーシス対処法として、人体では骨のカルシウムを奪う仕組みがあります。
カルシウムはアルカリ性なのでこれを血液に溶かす事でバランスを保つ事ができますが、これは骨のカルシウム不足を招きますので、骨粗鬆症の原因となります。
むくむ位ならまだいいですが、骨粗鬆症は洒落になりません。
アシドーシスには十分注意して下さい。
体を冷やす
では次、水を飲み過ぎると体温が下がるという意見があります。
この説が浮上した理由として考えられるのは、まず体温より低い飲食物を取り込む事により、熱を奪われるという発想かと思います。
しかし、僕達は恒温動物で体温調節機能があります。
温度の低いものに触れると体内で熱を産生し、体温を維持するようになっています。
もし、飢餓状態でエネルギーが完全に枯渇していて体温を上げられない状態に陥っていたら可能性はありますが、普通は水程度で体が冷える事は考えにくいと思います。
まして、水はそもそも体温調節の役割を持っています。
水は温度の変化が緩やかという性質を持っており、生体の体温を安定させる事に貢献しています。
もし、水分量が少なかったら外気温の変化に応じて体温が変化しやすくなるため、体温が激減する事も考えられます。
さて、体温降下説の理由としてもう1つ考えられるのは、小便が出るというものです。
確かに水をたくさん飲むと小便もたくさん出ます。
そして、保温性がある水分を放出した場合、一瞬その器官の温度が低下します。
しかし、この温度変化は非常に小さく一時的なもので、実感できる程に体温が下がるとは思えません。
発汗あれば納得できます。
汗は蒸発する時に体の表面の熱を奪う体温調節機能で、明確に体温を下げる働きを持っています。
唐辛子などに入っている辛味成分はこの働きを持っており、インドなどの暑い国でよく使われるのはそのためです。
しかし、水にそんな成分は入っていませんから、運動でもしない限り、汗は出て来ません。
そう考えると、やはり体温を下げる程の効果はほとんど無いのではないかと思うのです。
唯一、考えられるとすると、ある種の硬水の過剰摂取です。
硬水とはミネラルが豊富な水の事ですが、中にはカリウムが大量に入っているものもあります。
人間が体温を下げる方法は基本的に先程の発汗と皮膚の血管拡張の2つなのですが、カリウムは血管拡張作用があり、体熱を放出する働きがあります。
バナナやアボカドなど南国の野菜や果物にカリウムが豊富なのはそのためです。
ですから、カリウム豊富な硬水をたくさん飲む事で体温降下が現れてくる可能性はあると思います。
ただ、カリウムはナトリウムにより相殺されるのでバランスが取れていれば大丈夫だと思いますし、まして普通の水であればそんな事は起こりません。
という事で、やはり水の飲み過ぎで体温が下がるというのは難しいのではないかという結論に至ります。
ちなみに、水を飲まな過ぎて脱水状態になると発汗などの熱放散機能が働かなくなり体温は上昇します。
しかし、これはただの熱中症の事ですから、体温を上げたいからと言って、水分を制限する事は止めるべきだと思います。
水毒
最後、水を飲み過ぎる事で、頭痛、目まい、便秘、更にはアトピー、鼻炎、喘息などが起こる事について。
この説はどういう理屈で導かれているのかわかりませんが、どうやら水毒という漢方医学の症状で言われる事のようです。
ウィキさんに問い合わせてみると水毒とは、
| (すいどく)とは、漢方医学において、人体に水分が溜まり、 排出されないことによって起こるとされる諸々の症状のこと。冷え・めまい・頭痛・アトピー・鼻炎・喘息・疲労感・ 頭重感・むくみなどは水毒による症状であることがある。 水分の摂取量が多いにもかかわらず1日の排尿量が極端に多かったり少なかったり、 原因として水分の摂りすぎや運動不足で水分が排出されないことが挙げられる。 特に日本の気候では大気中の湿度が高いため、 |
と書かれています。
これを見ればわかる通り、悪いのは水ではなく、水分が適切に排泄されない事です。
むくみの問題と同じです。
水が入ってくるのが問題ではなく、出ていかない事が根本的な問題です。
その原因は先程のアシドーシスなどもそうですし、ここに書かれている通り、運動不足もあるでしょう。
皮膚に問題があって発汗機能が衰えているのかもしれませんし、腎機能の障害で小便の量が減る事で起こる事もあると思います。
特に腎臓においては、「むくみの本当の原因は腎不全にある」と言う専門家もいるくらいですから、可能性は高いと思います。
いずれにせよ、大切なのは問題の矛先です。
水毒の問題は入口ではなく出口にあります。
出口の機能不全により水が排泄されなくなった事が問題です。
その根本的問題に目を向けず、安易に入口を制限しようとするのはいかがかと僕は思うのです。
どこかで話しましたが、動脈硬化の本当の原因は血管を詰まらせるコレステロール本体にあるのではなく、コレステロールが集まる程、動脈が傷ついている事です。
水毒にせよ、動脈硬化にせよ、僕達はどうしても目先の問題に振り回されがちですが、本当の原因は全く別のところにある事を常に考えておかなければいけないと思うのです。
という事で長くなりましたが、総じて水の摂り過ぎが問題になる事は無い、という過程を経る事となり、だったらメリットのある水はたくさん飲む方が良いという結論に、「今のところは」至っているのであります。
飲むべき量は?
最後に具体的にどの位を目安に飲むべきかを話しておきますが、人間の体が排泄する水は1日約2.5Lなので、最低でもこれを補給する位は必要です。
詳細な分配を言えば、飲み水で1L、食べ物の水分で1L、栄養の代謝過程で出る水分で0.5L、これで合計2.5Lです。
ただ、飲み過ぎて危険な事は無いと考えれば、不足する事がないようもう少し多めに見て、飲み水で1.5~2L位補給すると良いと思います。(個人的にはもっといっちゃっていいと思いますが)
後は各々の体で試して適切な量を見つけて下さい。
最初に言いましたが、一番大切なのは「実感」です。
それでは今日はこの辺で。
PS:
水はたくさん飲む事も大事ですが、それ以前に質が重要です。
最高のクオリティを誇る水はメルマガで紹介しています。

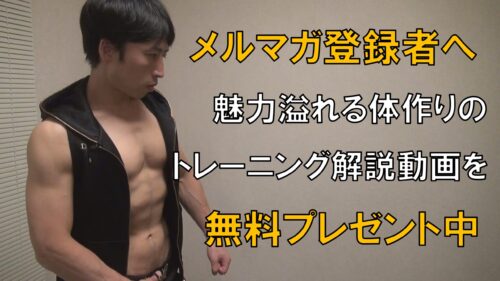




難しい話だと思います。
老若男女、運動の有無でそれぞれの水の必要量は違ってきますね。
ただ、昔の人たちはそれほど水を飲んでいたのでしょうか?
今みたいに自動販売機やコンビニもなく、大人はあまり水筒を持ち歩いていませんでした。
部活でも、飲むなと言われていましたが、倒れる人は今の方が多い気がします。
陰謀論と言われそうですが、厚労相が「2L飲め」と言うなら疑った方がいい気がします。
薬など西洋医学は否定派なので、政府と繋がっている今の医学の「常識」はとにかく疑ってかかっています。
また、食事が少食(お腹が空いたら食べる)がいいように、水分も喉が渇いたら飲むというのが自然な飲み方とも思います。
私の例で恐縮ですが、昔から水はあまり飲めなくて、たぶん1日500mlしか水としてはとっていません。
食事の水分量もしれています。
汗をかく運動の時はそれなりに飲みますせん。
食事もしれています。
汗をかく運動の時はそれなりに飲みますが。
40ですが、肌もきれいな方ですし、便秘になったことはありません。病気もいまのところなく元気です。
長文失礼しました。
飲み方・・でしょうね
一日4L目標・・時間がないから朝起きたら4L一気♪
なんて極端な事していると逆に毒になり得るかと。
体液濃度が急に薄くなるとか、肺に入って溺死するとか。
僕は成人してから喘息になりました。
水毒の説から、極力水を飲まない生活を始めて1年くらいになります。この1年間は喘息発作が一度も起きていません。ですが、完治したわけではないのです。喘息克服本を買って読んだところ、食前に水を飲め飲めとあり、その通りにしていましたが、悪化するばかりで1ヶ月で止めました。どっちが本当なのでしょうか?適量がつかめません。水を飲んで健康になった人たちの中に喘息が完治した方はいらっしゃいますでしょうか?いれば、もう一度水に挑戦してみたいです。
質問にお答えいただき、ありがとうございました。
浮腫みはナトリウムとカリウムの浸透圧によって起こるのでは?
カリウムを多く含む野菜や果物を多く摂取する事で改善されると思います。
いつもためになる記事を提供して下さりありがとうございます。
今年古希を迎えます。3年前にリウマチと診断されましたが、水素水の飲用で、数値(CRP)が劇的に下がりました。水素水についてのコメントを期待しております。
“CRPとは、もともと肺炎球菌という肺炎を起こす菌によって炎症がおこったり、組織が破壊されたりすると、この菌のC‐多糖体に反応する蛋白が
血液中に出現することからC‐反応性蛋白(CRP)と呼ばれていました。”