パフォーマンステストを受けて来ました。
最近は健康面や機能面を考えて、自分の体がどうなっているのか、定期的にチェックするようにしています。
どんなテストをしているかと言うと、色んな事をやってます。
バランス、安定性、可動性、左右差など、体を正しくコントロールできているかをチェックするものから、
パワー、バネ、持久力、敏捷性など、アスリートがやるようなものまで幅広く計測してみてます。
こうして定期的に体をチェックする事で、やってきた事の成果を確認したり、新たな課題を見つけて次のレベルへ進む足掛かりとしているのですが、今日はそんなテストの中から重要なものを1つ紹介したいと思います。
「体幹」の強さを測定するテストです。
体幹の重要性を今更細かく説明するつもりは無いですが、「体」の「幹」と書く通り、体幹はあらゆる動作で中心を担います。
立っている時、座っている時、動いている時、全部体幹が関わっているし、
逆に体幹が関わらない動きというのは存在しません。
そして、体幹が弱ければ腰痛になるし、手足の動きは制限されるし、
健康面も機能面も大きく損害を被る事になります。
逆に、体幹が強ければ怪我のリスクは劇的に下がって、
運動パフォーマンスは上がって行きます。
そんな重要な体幹ですが、今日はその強さを測定する方法をお伝えします。
一般的には余り知られていないものだと思いますが、割と使い勝手が良く、日常生活との関連性も見えやすいので、良かったら参考にして下さい。
体幹の測定方法
やり方はシンプルです。
自分の体重の75%の重量のダンベルを用意し、両手に持って限界が来るまで歩きます。
そして、歩いた距離(フィート)と時間(秒)を測定し、それらと0.75(体重の75%)を掛け算します。
この値を「Carry Energy」と呼び、体幹の強さを示すスコアとなります。
例えば、体重が60kgだとしましょう。
その75%の重量は45kgです。
ダンベルなので2つに分けると片方22.5kgになるわけですが、それを両手に持って、ひたすら歩きます。
歩くのは別に一直線である必要は無く、部屋でやるなら往復でも円を描いても何でも構いません。
そして、歩いている内に握力が無くなっていって、ダンベルを落としそうになったら、そこでストップです。
仮に50メートル、1分間歩けたとしたら、
164フィート(50メートル)×60秒×0.75=7,380
これが体幹の強さを示す値となります。
体幹と握力
「何でこれが体幹のテストになるんだ?むしろ握力のテストでは?」
と思われるかもしれませんが、正真正銘これは「体幹」のテストです。
どういう事か説明しましょう。
体幹が弱い人は体がブレやすいので、重りが前後左右に揺れやすくなります。
そして、重りの揺れが大きくなるほど持ちにくくなるので、それを保持するために強く握り込む必要が出て来ます。
すると握力が早く無くなり、短い距離、短い時間しか重りを運べなくなります。
逆に、体幹が強い人は体がブレないので重りの揺れがほとんど起こらず、手は握り込むというよりも、軽く引っ掛けておくだけで済みます。
すると握力の消耗が最小限に抑えられ、結果として長い距離、長い時間を運べるようになります。
これが体幹のテストとして採用されている理由です。
なかなかユニークな測定方法だと思いますが、大変理に適っていて、アスリートの指標にもなっています。
世界中の色んなスポーツ選手の間でも行われているので、信頼性もかなり高いと思います。
そう言えば、優れた柔道選手は握力が一般人と変わらないそうですが、その理由は正にこのテストから見えて来ると思います。
柔道と言うと、相手の襟を掴んで投げるため、強い握力が必要かと思われがちですが、実はそうではありません。
本当に強い柔道選手は体幹が強いので握力はほとんど必要とせず、相手の襟に指を引っ掛けておくだけでいいのです。
逆に言うと、握力が強いという事は体幹が弱い可能性があり、競技ではイマイチな結果しか残せなかったりします。
体幹と健康
横道に逸れたので話を戻しましょう。
先程のCarry Energyですが、基準値として示されているのは、
250フィート(約76メートル)×90秒×0.75=16,875
です。
これ位の数字はクリアしてないとマズイですという閾値で、ちゃんと運動している人ならいけるのではないかと思います。
そして僕のスコアは、
450フィート(約137メートル)×218秒×0.75=73,575
でした。
基準値の4倍位でプロスポーツ選手と同程度らしいですが、これは別に自慢したくて見せているわけでは無く、冷静に数字を比較してもらうために出しています。
僕は基準値の人と比べて、重りを運ぶ能力が4倍あります。
つまり、仕事が4倍出来ます(物理学の仕事量とは違います)。
逆に言うと、同じ量の仕事をするのに、僕は4分の1しか体力を使いません。
つまり、それだけエネルギーが余りやすいという事であり、それだけ疲れにくい体になっているという事です。
これは健康を考える上でとても大切な事だと思います。
エネルギーが余って疲れにくい体になっていれば、免疫、ホルモン、酵素なども活発に動いてくれますから、体に異変があった時にすぐに対応できます。
病原菌も即撃退できるし、怪我した時の回復も早まります。
そして、多くの健康法はこうしたエネルギーの余剰を食生活からアプローチしますが、そこには限界があります。
食事量を減らしたり、体の負担のかかる脂質を避けたり、確かにそれも大事なのですが、それよりももっと根本的な動作の質を改善する事が大事だと思っています。
特に今回お話したような体幹の強さを改善していけると、数字からも分かるように目に見えてエネルギーロスが減ります。
体幹の強さを手に入れるという事は、何も競技に活かすという事だけでなく、日常生活のクオリティを高めて健康的な体を手に入れるという意味においても、非常に有意義なものなのです。
別にアブローラーを立ってやりたいから体幹を強くするわけではありません。
デッドリフトやスクワットの記録を伸ばすためにやるわけでもありません。
勿論それらも可能になりますが、もっと実生活を効率化するために、体幹の強さを手に入れる必要があるのです。
この考えを持っているかどうかで、健康レベルは大分変わると思います。
正しい食生活のみでアプローチしていく人、正しい動作まで考えてアプローチしていく人、両者の間には数年後に大きな差が出るはずです。
体幹を強くする方法
では体幹を強くするにはどんなトレーニングが良いのか?
表面的な事を言うと、懸垂にはその効果があると思います。
懸垂はバーを握る指以外の体が完全にフリーになるため、体が揺れないよう体幹をコントロールする必要があるからです。
よく懸垂で体が揺れてしまってテンポよく出来なかったり、先に握力が無くなってしまう人がいますが、それは体幹が甘いからです。
しっかり体幹を固めてブレないようにできれば、テンポ良くサクサクできるし、今回紹介したテスト同様、握力をほとんど使わずに済みます。
ですから、懸垂を正しく出来るようになると、体幹は強くなります。
これはラットプルでは得られないメリットです。
ラットプルは脚部を固定してくれるため、わざわざ体幹を固める必要がありません。
これは背中の筋肉に集中しやすくしてくれて、筋肥大効果を高めてはくれますが、引き換えに体幹の強さが失われるリスクにもなっているわけです。
ちなみに、ラットプルに限らず、基本的にマシンは体幹が弱まる可能性があります。
マシンは特定の筋肉にフォーカスしやすいよう外部から体を固定しれくるので、体幹のパワーを使う必要無くなるからです。
人間の体はよくやる事に最適化されるので、脳が必要無いと判断したら、その機能は衰える一方です。
そう言う意味では、筋トレなら自重やフリーウェイトが良いかと思います。
外部からの補助が全くない状態で体を安定させなければいけないので、少なくとも体幹が弱くなるような事にはならないはずですし、上手くやれば体幹は強くなっていくはずです。
ただ、根本的に体幹を強くしたいのであれば、筋トレよりも呼吸や腹圧のトレーニングが重要です。
体幹の強さはいかに腹筋に頼らずにお腹を固められるかにかかって来るので、表層の筋より横隔膜など深部の筋を鍛えるのが最優先になります。
この辺は割と地味なトレーニングなので、取っつきにくいかもしれませんが、長期的なパフォーマンスを考える上では非常に大事です。
詳しくはメルマガでお伝えしているので、興味あれば登録していって下さい。
既にメルマガ読者の方はもう登録する必要はありませんので、今まで送ったコンテンツを復習してもらえたらと思います。
そんなわけでダラダラと書いて来ましたが、今回は体幹の強さの測定法と、その高め方について書いてみました。
少しでも参考になれば幸いです。


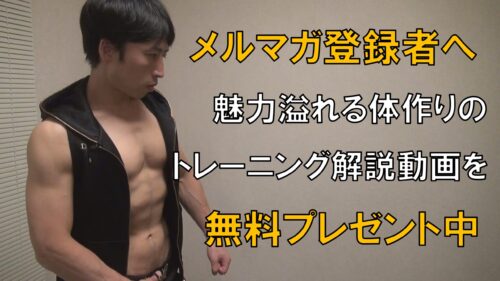




いつも拝見させて頂いています。
この記事の冒頭でご紹介されている、
パフォーマンステストに興味があります。
どこでそういったものを受けられるのでしょうか。
差し支えなけば教えて頂きたいです。