以前、F1と固定種の育て比べの動画を出した事があります。
興味深く見てくれて感想まで送ってくれた方もいましたが、一方で種の事情を余り知らない人は「なんのこっちゃ」という感じになっていたようです。
そこで、今回は農業の世界では長らく物議を醸し続けている「F1」というものについて分かり易く説明したいと思います。
F1についてはネット上にも既に多くの情報が出回っていますが、個人的には正確性に欠けるものが多いなと感じています。
また、「F1は悪」「雄性不稔は陰謀」と言うような偏見も多く、閲覧する方に色々と誤解が生じているようにも思います。
勿論、中立の立場で丁寧に書いてあるものもありますが、そういうものは大抵分かりにくい。
農業の専門用語をバシバシ使って説明しているため、一般人が短時間で理解するのは難しいだろうと感じます。
と言う事で、僕がしゃしゃり出てみます。
なるべく正確に、平等に、そして分かり易く、F1というものを解説させて頂きます。
- そもそもF1とは何なのか?
- どういう経緯で誕生したのか?
- 何が問題と言われているのか?
- 実生活への影響は?
- セットで出て来る固定種って何?
- 種無し果物ってF1なの?
などなど、これを見ればF1の概要がほとんど理解できると思うので、興味があれば見ていって下さい。
F1とは?
正式名称は「First Filial Generation」。
日本語にすると「一代雑種育種」。
別名「ハイブリッド」。
歴史的には割と新しい品種改良の1つで、日本語名から分かるように、品種の異なるものを掛け合わせて作った雑種の事です。
ざっくばらんに言えば、両親の良いとこ取りで作った強い子どもです。
雑種には「雑種強勢」という性質が働くため、野菜も生育が良くなり、収量、品質、耐病性などが向上します。
これ自体は至極真っ当な事だと思います。
人間でも近親相姦より、血筋の異なる者同士から生まれた子どもの方が健康状態は良くなります。
犬や馬も血統書付きのサラブレッドより、ミックスの方が病気になりにくい事は知られています。
しかも、植物のF1に関しては、メンデルの法則に従って、子どもには優性の特徴だけが現れ、品質と形質が揃います。
少し中学校の理科を思い出してみましょう。
優性遺伝子「A」と劣性遺伝子「B」があるとして、「AA」の親と「BB」の親を組み合わせると、子どもは全て「AB」となります。
そして、「AB」の品質や形質は全て優性の「A」が適応されます(図で言うと、子どもは全て緑色のエンドウ豆になる)。
そうなれば、味や形が完全に揃うため、非常に流通させやすくなります。
運びやく、並べやく、大きさや美味しさが違うというクレームも無くなり、効率的に食品をお茶の間に届けられるようになるわけです。
こうした理由でF1は急速に普及しました。
今では食卓に並ぶ果物や野菜はほぼF1です。
家庭菜園をしたり、特別な農家から仕入れていない限りF1の植物です。
F2の問題
ただ、F1には1つ問題がありました。
それがF2の存在です。
先程言った通り、雑種一代目の「AB」は全て優性の特徴を出しますが、その「AB」同士が掛け合わさった雑種二代目には「BB」が現れ始めます。
そして、「BB」は優性遺伝子を持たないので、品質や形質は「B」が適応されます(図で言うと、孫に黄色のエンドウ豆が出て来る)。
そしてこれ以降、掛け合わせによりどんどん品質と形質が揃わなくなり、結果として流通させにくい状況に陥ってしまうわけです。
そのための対策がF1に子どもを作らせないという処置ですが、これがよく問題視される雄性不稔に繋がって行く事になります。
子どもを作れないF1
F1に子どもを作らせないために、いきなり雄性不稔が適応されたわけではなく、大きく3つのステップがあったので簡単に紹介しておきます。
1.除雄
歴史的に一番最初に行われた対応です。
手作業で花の雄しべを取り除くという非常にシンプルな方法でした。
最初に除雄を行ったのは日本人で、1924年にナスで行われた記録があります。
世界最初のF1と言われています。
2.自家不和合性の利用
自家不和合性とは、近親相姦を防ぐための性質の事ですが、具体的には花粉が自分の柱頭に受粉しても受精に至らない事を言います。
アブラナ科のハクサイやキャベツなどがこの性質を持っていますが、実はつぼみの時にピンセットで開いて自分の花粉を付けると受粉します。
すると、自分のクローンが大量生産される事になるわけですが、花が咲いた時には自家不和合性により自分達で勝手に受粉が出来なくなっています。
簡潔に言うと、自分達だけでは受粉できない者同士を並べて育てる事で、勝手に一代で終わらせる状況を作ったという事です。
3.雄性不稔の利用
これが何かと話題に上がる方法になりますが、一言で言えば、母親に不妊症の遺伝子を持たせてしまいます。
子どもはその不妊症の遺伝子を受け継ぐため、結果的に一代で終わる雑種が出来上がります。
1944年にこれを利用したF1タマネギが誕生し、それ以来この方法が主要なものとなりました。
そして、この辺りからF1の評価が変わって行きます。
F1の悪評
F1の当初の目的は雑種強勢効果と、品質や形質を揃える事にありました。
既に述べた通り、収穫量を増やして流通をスムーズにし、食品の安定的な供給を図れるようにするためです。
しかし、一代で終わるF1種は自家採種が出来ないために、毎年種会社から種を買う必要が出て来ます。
すると、種会社としては利益を出すために、いかに効率的に子どもを作れないF1を作るかという事に集中するようになります。
そこに雄性不稔という手段が加わり、手段が目的に変わって行きました。
雄性不稔の技術は加速し、今では不妊症の親を見つけるというよりも、遺伝子組み換えで雄性不稔を組み込むという流れも出て来ました。
それを揶揄して「自殺する食品」なんて過激な言葉も出て来ましたが、こうした流れがF1の悪評を生んだ1つの要因になって行きます。
要は「儲けを追求して無茶苦茶やってる」という風に見えたのです。
それに加えて、毎年種を買う農家が苦しんでいる状況が取り上げられ、F1に対する批判は一部の間でかなり大きくなりました。
ただ、個人的にこの流れ自体は仕方ないのかなとも思います。
F1は食糧不足を解消し、世界中から飢えを減らす希望になったわけで、ビジネスがそこに集中するのも当たり前と言えば当たり前ですし、農家はそこに適応して行かねばならないと考えています。
実際、こうした逆境を上手く利用している農家もたくさんいて、全員が損害を被っているわけではありません。
つまり、大きな目で見て、人類が越えるべき壁の1つと思うのです。
ただ、そういった感情的な問題とは別に、気になる事があるのも事実です。
それは「F1は体に悪く無いのか?」という素朴な疑問です。
F1は体に悪いのか?
F1は危ないと考える人達の意見で中心となっているのは、「将来的に無精子症になるリスクが上がる」と言うものです。
と言うのも、そもそも雄性不稔というものは、ミトコンドリア遺伝子の異常から起こる事がわかったためです。
現在、ヒトの男性不妊症はミトコンドリア異常が原因と言われています。
動物実験でも、ミトコンドリアの遺伝子が傷つくと、精子の数や運動量が減り、不妊症上や無精子症になる事がわかっています。
ちなみに、ミトコンドリア遺伝子は母親からのみ子どもに継承されるため、F1を作る際は母株に雄性不稔の能力が必要になります。
話を戻しますが、ミトコンドリアに異常を抱えたF1植物を食べると、食べた者も種が作れない無精子症になるのでは無いか?という仮説があります。
これに関連して、野口種苗研究所の野口さんは、ミツバチが原因不明に大量に失踪する蜂群崩壊症候群(CCD)の原因を、F1と推測していたりもします。
こういう事を聞くと、何だか最もらしいように聞こえますが、ただ現時点でそういった事実が認められたデータはありません。
一応、ここ100年くらいで精子の数が減っているという事実や不妊症の人が増えていると言うデータがあるにはあります。
しかし、その原因は電磁波だったり、医薬品であったり、他の要因も大きいようにも捉える事が出来て、一概にF1と結びつける事が出来ません。
雄性不稔の歴史はまだまだ浅く、人体にどのような影響が出るのかは現段階ではほぼわかっておらず、推測の域を出ないのが現状です。
個人的には何となく嫌だなと感じつつも、悪影響があった体感は無く、またインフラ化するF1に抗う事は難しいと、複雑な気持ちでいます。
身近なF1
実害があるかはわからないけれど、何となく嫌な感じがするF1ですが、最も身近なものとして普及しているのはトマトです。
そもそもトマトは栽培面積・生産量ともに世界一の野菜で、品種改良のスピードも先陣をひた走って来ました。
トマトは果実食用、ジュース用、ペースト用など用途が幅広く、世界中で消費量が非常に多いためです。
勿論、一代雑種の歴史も最も古く、最も広く適応されている野菜で、今では世界中のトマトのほとんどがF1になっています。
割合的に多いもので言えば、テンサイもそうで、世界的にほぼ全てF1になっていると言えます。
テンサイはマクロビなどで推奨されており、何となく昔ながらの自然な甘味料というイメージがあるかもしれませんが、実は人類との付き合いは非常に短くて、品種改良では最先端を行く科学と親和性の高い植物なのです。
逆に、F1がほとんど無いのが米です。
特に日本では普及しておらず、日本の米でF1は1%弱しかありません。
一応、三井化学アグロが「みつひかり」と言うF1米を出していますが、有名なのはそれくらいではないでしょうか。
尚、中国は最もF1米が盛んで、稲全面積の58%占めています。
今後、世界の流れ的に米のF1化が進むのかどうかは興味深いところです。
固定種とは?
この話もしておかねばなりません。
F1との対比として出て来る言葉で「固定種」というものがあります。
他に「在来種」「古来種」というような呼び方もされますが、今回の文脈に沿って言えば、F1の親の純血種に当たるものです。
先程のメンデルの法則を借りれば、「AA」と「BB」の子どもの「AB」がF1で、親の「AA」が固定種です。
ちなみに、僕が動画にアップしているF1と固定種の育て比べですが、この辺を少し勘違いしやすいので気を付けて下さい。
例えば、「聖護院大根」の比較であれば、固定種は「純粋な聖護院大根」で、F1は「純粋な聖護院大根」×「雄性不稔の母株」で作られた雑種です。
固定種の方は親、F1の方は子どもに当たりますので、完全に同じ立場の比較では無い事を知っておいてもらえたらと思います。
話を戻しますが、固定種のデメリットとしては雑種強勢が働いていないので、F1より病原菌などに弱い可能性があります。
また、自家採種が出来て子どもも作れますが、それと引き換えに子孫の品質や形質はバラバラになって行きます。
メリットとしては、味に個性があるという事でしょうか。
美味しいかどうかは個人の好みによりますが、均一でない個性豊かな味が楽しめると思います。
それと、雄性不稔のリスクを心配する必要がありません。
種無し果実の正体
最後に、F1と混合しがちな種無し果物について話しておきます。
よく勘違いされる方がいますが、種無し果実は雄性不稔のF1とは全く別物です。
例えば、種無しブドウの種が無いのは、ジベレリン液に浸す事で種を溶かしているためです。
ジベレリンとは植物ホルモンの一種ですが、現在では農薬や果実の落下防止などにも用いられます。
また、果物では無いですが、スイカはコルヒチンという物質を使用する事で種無しにする事が出来ます。
それと、種無しカキは品種改良により、受精した胚を退化させて作ります。
これらの健康被害についても議論される事がありますが、F1同様、今のところ結論は出ていません。
ただ、個人的には種有りの方を好んで食べています。
という事で最後は蛇足になってしまいましたが、今回はF1についてなるべく平等な立場から解説を試みてみました。
少しでも参考になれば幸いです。
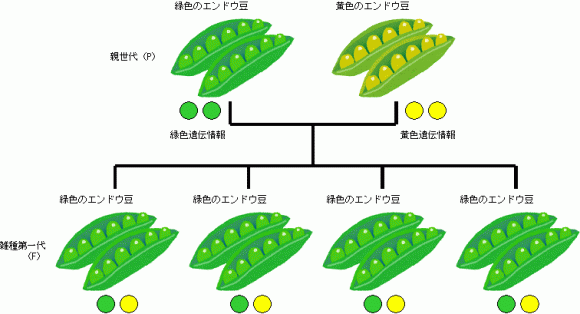
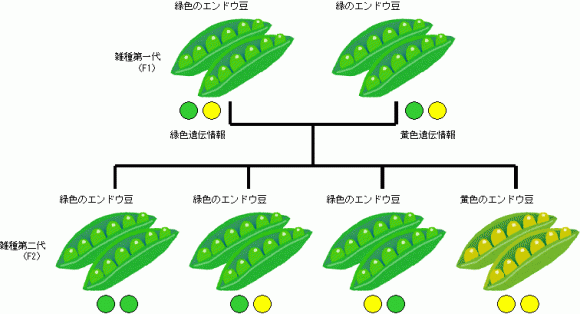
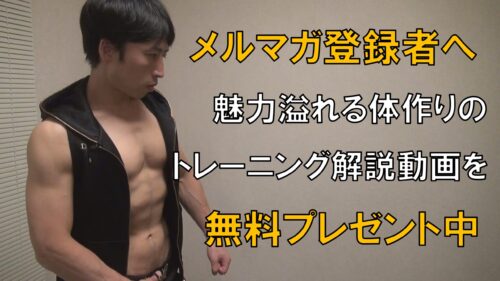




コメント